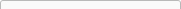匂いフェチ官能小説
第6弾
【 ふたりの匂い 】
6/11
「はぁっ……はぁっ……!」
官能の嵐が吹き過ぎた後。
杏子は前のめりに手をついたまま、
荒い息を吐いていた。
口に咥えていたはずのパンティは、
意識の朦朧とする中で、
ベッドの上に落としてしまっていた。
丸まって棒状になった白い布地が、
結菜の脚の間に転がっている。
(は……ぁ……。すっごい良かったぁ……。
こんなに激しくイッたの、
ほんと久しぶりだわ……!)
最高に匂うパンティを口に咥えたまま、
愛しい後輩の顔に
股間を擦り付けて達した絶頂。
それは、杏子のこれまでの性体験の中でも
一、二を争う至福の瞬間だった。
問題は、
歓喜の発作があまりに激しすぎたせいで、
今までにない量の失禁をしてしまったことだ。
イッいる最中は何もかも忘れて
悦びに浸っていた杏子だったが、
当然、その大きな代償は
受け止めなければならない。
とはいえ、正直なところ、
振り向いてベッドの上の惨状を見るのが怖かった。
(あぁ……。
でも、あんなに気持ちいい思いをしたんだもん…
…。ベッドを買い替えることになっても、
まぁしょうがないわ……)
さっきまで咥えていた結菜のパンティを
お守りがわりに握りしめ、
覚悟を決めて身体を起こす。
(さぁて……。
どれだけ酷いことになっているのかな……)
ゆっくりと振り返り、
視線を結菜の顔のほうへと向けた。
すると……。
(あれっ?
思ったよりもビチョビチョになってない……?)
目に入ったのは、
白と水色のしましまパンティを口に含んだまま
グッタリしている結菜と、
それほど濡れた様子のないシーツだった。
(なんでっ……?)
あの時の感覚からすると、
おそらくコップ半分くらいの量は
出てしまっていたように思う。
実際、「ちょっと漏らした」では済まないような
尿臭が、結菜の顔の辺りから漂ってきていた。
(ちょっと……。じゃあ、どこ行っちゃったの、
私のおしっこ……?)
こうなると、逆に不安になってくる。
念のため壁のほうも見てみたが、
そちらにも飛び散っている様子はなかった。
(もしかして、ぜんぶ結菜の服に
掛かっちゃったのかな……)
絶頂したまま気を失っているらしい
結菜に近づき、
右手で彼女の胸元に触れてみる。
が、ここも大丈夫だった。
タートルネックの首回りには
若干の湿り気を感じたものの、
これは単に結菜が汗ばんでいるだけだろう。
(あれー、じゃあどこに……。あっ……!)
そこでようやく杏子は、
結菜の咥え込んでいる自分のパンティが
グッショリと濡れた色になっていることに気付いた。
(なるほど、そういうこと!)
つまり、杏子の漏らしたおしっこは、
ほとんどが結菜の口に押し込まれた
木綿生地に染み込んでいたということだ。
たしかに、鼻に股間を擦り付けていた時の
角度を考えれば納得がいく。
(あぁ、良かった……。
あんなエッチな姿勢でオナニーし合ってたおかげで、
ベッドを汚さないで済んだんだわ……)
これがシックスナインの形ではなく、
「向かい合わせでのオナニーの見せっこ」
だったら、失禁したものはすべてシーツ、
そしてその下のマットレスへと
染み込んでしまっていただろう。
偶然とは言え、
杏子は自分たちの変態さに
感謝したい気持ちになっていた。
(ふふっ。ありがとうね、結菜。
あなたとのエッチじゃなかったら、
きっとベッドを買い替えることになってたわ)
なんだか急に結菜のことが愛しくなってきて、
彼女に身を寄せていった。
「ん……ふぅん」
ぼんやりと意識を取り戻してきたのか、
結菜が小さく喘いだ。
ますます胸がキュンとしてきて、
杏子はそのまま彼女に覆いかぶさっていった。
仰向けの結菜の胸に自分の胸を合わせながら、
うっとりと頬を寄せていく。
彼女の顔から漂ってくるのは、
湿気を帯びたアンモニアの香り。
そして、
その子供っぽい横顔には似つかわしくない、
淫らにすえた恥垢の匂い……。
(あん……。こんなに可愛い結菜が、
こんなにエッチな匂いにまみれてるなんて……)
その清純そうな見た目と、
漂わせている卑猥な香りとのギャップに、
秘唇がジーンと熱くなってきてしまう。
杏子の中の倒錯した欲求が、
再びムクムクと膨らみ始めていた。
「はぁぁ、結菜ぁ……」
気がつけば杏子は、
結菜の頬に舌を這わせ始めていた。
「ん……ぁ……。ん……レロ……」
まず最初に感じたのは、
結菜がいつも使っているファンデーションの香り。
そのまま舌を這わせていくと、
微かながら尿の匂いが混じり始めた。
「んんんっ……。レロ、レロ……」
さらに舌を進めてゆく。
結菜の鼻の脇に近づくにつれて、
はっきりとしたおしっこの塩気が
感じられるようになってきた。
やがてなまなましい女蜜の風味、
淫靡な恥垢のアロマまでもが漂いだし、
杏子はもうメロメロになってきてしまった。
(はぁぁっ……!
この子、こんなにいやらしい匂いのする
私のアソコ押し付けられながら
オナニーしてたんだっ……!
こんなエッチな匂いにまみれてイッたら、
そりゃ気も失っちゃうわね……)
杏子自身も、
興奮のあまり瞬間的にではあるが
思考が途切れるのを感じていた。
口に含んでいたはずのパンティを
いつの間にか落としてしまっていたのだから、
実際に数秒単位で意識が飛んでいたのだろう。
それでも完全に失神しなかったのは、
結菜の上になっていたために、
体重を掛けすぎて彼女が窒息してしまわないよう
必死で気を払っていたからだ。
対して、
そういったことを気にする必要のなかった結菜は、
荒れ狂う官能の波にすっかり身を委ね、
そのまま意識が途絶えるまで快感を
貪り尽したのだろう。
杏子はそんな結菜を羨ましく思う一方、
嬉しくもあった。
(うふふっ。
この子がこんなに自分をさらけ出せるのは、
私の前だけだもんね)
彼女の両親ですら知らない本当の結菜を、
自分はこんなにも深く知っている。
杏子は血の繋がり以上の絆を感じて、
キューンと胸が熱くなる思いだった。
やがて、杏子の中に強い感情が生まれてきた。
(結菜がどんな味と匂いを感じながら
オナニーしてたのか、もっとちゃんと知りたい。
今なら、この子とキスすればわかるはずよね……)
結菜と直接キスをするためには、
彼女が咥えたままでいるパンティを
どかさなくてはならない。
杏子はさっそく、結菜の口に向かって
手を伸ばしていった。
(あっ!)
あと数センチでパンティに触れる、
というところで、杏子はピタリと手を止めた。
ちょっとしたことではあるが、
素敵なアイデアが頭に浮かんだからだ。
(どうせなら……ね?)
杏子の左手の中には、
さっきまで自分の口に含んでいた
結菜のパンティがあった。
ベッドの被害が最小限であって欲しい、
との思いから、お守りがわりに
握りしめていたものだ。
その赤いリボンの付いた白い布地を、
杏子は優しい手付きで広げていった。
そうして結菜のパンティで右手を覆った上で、
改めて彼女の口元に手を伸ばしてゆく。
「ごめんね。結菜のお口のパンティ、
ちょっとどかすからね」
愛らしい唇の間に挟まれた布地を、
手の中のパンティで包むようにして掴み出す。
下側の端が口から抜け出る時、
少し黄ばんだネバネバの唾液が
つぅーっと糸を引いた。
そのヌルつきも含めて、
すべてを右手のパンティでくるみ込む。
「うふふふっ。
ほらぁ、私と結菜が穿きっぱなしだったパンティ、
こんな風にぎゅうって抱き合ってるよ。
ううん、抱き合ってるっていうより、
結菜のパンティが私のを抱きしめてくれてるって
感じかなぁ。ねぇねぇ、結菜も見てー」
次第に気持ちが高揚してきた杏子は、
自分一人で楽しんでいるのがもったいなくなり、
同じ喜びを共有してくれる
唯一の相手を揺り起こしていった。
アンジェリークコラム