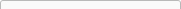匂いフェチ官能小説
第6弾
【 ふたりの匂い 】
2/11
台所もかねた狭い廊下を抜けて、
六畳ほどの広さの部屋に入る。
左側にはしっかりした作りのスチールベッド。
右側にはテーブルや洋服ダンス、
そして本棚といったものが並んでいた。
「電車止まっちゃって大変だったね。
喉かわいたんじゃない?」
杏子が振り向いて声を掛けると、
後ろについてきていた結菜はこくり、
と無言で頷いた。
「緑茶でいい?
ポットにお湯が残ってるから、
それならすぐに入れられるよ?」
問いかける杏子に対し、
一瞬頷きかかった結菜だったが、
直後に大きく首を振ってそれを打ち消した。
「ん? コーヒーか紅茶が良かった?
それならお湯を沸かすけど」
しかし、その言葉にも結菜は首を振る。
かわりに、上目遣いで
じっと杏子の顔を見つめてきた。
「喉かわいてるんでしょう?
何か飲みたいんじゃない?」
「はい……。だから、杏子さんの……」
ようやく口を開いた結菜だったが、
その声は途中から急速に弱まり消えてしまった。
「ん? なぁに?」
と杏子が聞くと、
結菜の顔がカァッと赤く染まった。
それでようやく彼女の求めているものが
何なのかを杏子は悟った。
(ははぁ。そういうことね。
この子、私の唾を飲みたいんだ)
とはいえ、
すぐに唾液を飲ませてあげる気にはならなかった。
なにせ自分は、あれだけの長い時間
おあずけに近い状況で悶々とさせられていたのだ。
その時のやきもきした気持ちを、
少しくらいは結菜にも味わわせてやりたかった。
「ダメじゃない。何を飲みたいのか、
ちゃんと口に出してお願いしないと」
そう言って手を伸ばし、
結菜の唇を指先で妖しくなぞる。
「で、でも……」
「ちゃんとお願いしないとあげないよ?」
結菜の下あごに手をあて、
クイッと顔を上向かせる。
そのまま右手を広げて彼女の両頬を挟み込み、
プニプニと掴み上げて弄ぶ。
「はぅ……」
結菜が泣きそうな表情で眉根を寄せた。
「うふふっ。変な顏」
そんな意地悪をしながらも杏子は、
口の中の唾液を静かに集め始めていた。
言ってみれば、十分な量の唾液が溜まるまでの
時間稼ぎだ。
「あ、う……」
その愛らしい顔を変な形に歪められつつも、
結菜は物欲しそうな目で
杏子の口元を見つめてくる。
やがて彼女は意を決したようにこう切り出した。
「く、ください、杏子さんの……その……」
が、その声は途中から尻すぼみになり、
最後まで続くことはなかった。
喉元まで出かかっているのに、
なぜかその言葉を口にできない結菜。
この上ない変態のくせに
そんなシャイな一面があるところも、
杏子には可愛くてならなかった。
(ほらほら。せっかくたくさん溜まってきたのに、
早くお願いしないと飲み込んじゃうぞー?)
わざとらしく、
口の中でクチュクチュと唾液を巡らせてみせる。
湿ったその音は当然目の前の結菜にも
聞こえているはずだ。
「あ、あ……」
自分の欲しい物の存在が分かったことで、
相当興奮が高まっているのだろう。
結菜は上気した表情で
杏子の色っぽい唇を見上げている。
それでも、
彼女の口から決定的な言葉は出てこなかった。
(あれー? 喉かわいてるはずなのに、
結構頑張るわねぇ。
も、お願いしないとあげないわよ?)
結菜に顔を近づけ、
さらに唾液をグチュグチュいわせてみせた。
しかし彼女は、逆に黙り込んでしまった。
声を出すかわりに、ハァハァと呼吸を荒げている。
もしかしたら、
誘惑の度合いが強すぎたのかもしれない。
(あぁん、もう、じれったいわね!)
杏子は
逆に自分が焦らされているような気持ちに
なってきてしまった。
正直なところ
愛情を持って溜め込んだこの唾液を、
早く彼女の口に流し込んでやりたかった。
そしてそのまま唇を重ね、唾液塗れの舌で
ヌチャヌチャとしゃぶり合いたかった。
にもかかわらず、
結菜はまだお願いの言葉を口にしない。
(もうっ、
早くキスしたいのは私も一緒なのに……!)
溜め込んだ唾液は、
そろそろ限界に近い量に達しようとしていた。
いったん飲み込んでしまえば
さらに時間を引き伸ばすこともできるが、
自分の唾を自分で飲み込んでもただ虚しいだけだ。
しかも、このまま待っていたところで、
結菜が自分から折れるとは限らない。
(もういいわっ。こうなったら、
こっちから攻めて行ってやる!)
杏子は
目の前でモジモジしている後輩の身体を
ガバッと抱きしめていった。
そうやって大きな胸をグイグイと押し付けながら、
向こうが我慢出来なくなって
哀願してくるのを待つ。
「あぁっ……! 杏子さんっ」
対する結菜もまた、
ギュウッと情熱的にしがみついてきた。
杏子の首筋に顔を埋め、
くんくんと幸せそうに匂いを嗅いでいる。
顔の下で彼女の髪が揺れ動き、
汗っぽい匂いが鼻をかすめた。
「はぁっ……はぁっ……!」
結菜の呼吸がますます荒くなる。
抱きしめている身体全体が、
だんだん熱を帯びてくるのが分かる。
(ふふっ。
私の匂いを嗅いで相当興奮してるみたいね。
喉がカラカラに渇いてきて、
早く私の唾で潤したいじゃないの?)
自分が優位に立っていると見た杏子は、
挑発的な抱擁をさらに強めていった。
すると
いよいよ我慢できなくなってきたのか、
結菜の唇がチュッ、チュッ、
と杏子の首筋を吸い始めた。
それが徐々にあごへと向かい、
やがて口元近くまで接近してきた。
唇の温かく湿った感触が心地よく、
次第にうっとりしてきてしまう。
「ん……!」
思わず、甘い声を漏らしてしまった。
その時だ。
結菜の唇が、
いきなり杏子の口に重ね合わされてきた。
「ん? んーっ!」
突然、ものすごい吸引力が杏子の唇を襲った。
キュゥッと閉じ合わせていたはずの口先に
わずかな隙間ができ、
溜めに溜めた唾液をそこからジュルジュルと
吸い出されてしまう。
(そんなっ……! この子、ずるいっ!)
気がついた時には、
半分近くの唾液が口から消えていた。
近くでこくん、と結菜の喉が動いた気配があり、
続いて
「んふぅ……」
という満足そうな溜め息が聞こえてきた。
「はぁぁ……。
杏子さんの唾、すごくおいしいです……。
残りも、全部ください……」
唇を離して見上げてきた結菜の顔は、
もうすっかりとろけ切っていた。
こうしてエッチモードのスイッチが入ってしまえば
彼女は少しいやらしいくらいの言葉なら
平気で口にしてしまう。
杏子としては、
そうなる前の素の結菜にエッチなお願いを
させたかったのだが……。
(あーあ、私の唾飲んだせいで、
完全に切り替わっちゃってる……。
こうならないうちに
意地悪して楽しみたかったのに……)
とはいえ、結菜とキスしたくてたまらないのは
自分も一緒だった。
杏子は唇をすぼめると、
目元をボゥッと赤く染めて
舌を差し出してくる結菜の口に、
トロトロと温かい唾液を流し込んでいった。
ところどころに白い泡の混じった唾汁が、
一筋の柱となって桃色の舌の上に垂れ落ちてゆく。
結菜はそれを、
まるで極上のスイーツを味わうかのように
恍惚と受け止める。
「んっ……んっ……」
唾液の切れ目を見計らって口を閉じ、
こくり、こくり、と幸せそうに
飲み込んでゆく結菜。
(あーん、この子、
なんておいしそうに私の唾を飲むのかしら……)
後輩のそんな姿を見て、
杏子はゾクゾクする満足感が
湧き上がってくるのを感じていた。
口の中の唾液が無くなってしまうと、
杏子は目を閉じて結菜に口付けしていった。
そのまま舌を差し入れ、
彼女の甘い口腔をヌルヌルと舐め回していく。
「んっ……んんっ……」
「んんっ……んーっ……」
二人の鼻から色めいた吐息が漏れ始めた。
「んむっ、んんっ、んむむっ」
「はむむっ、んんっ、んんんっ」
それぞれの舌を絡み合わせ、
温かくネットリした感触を楽しむ。
その刺激で湧き出してくる唾を舌腹に載せ、
お互いの口へ送り込む。
そうやって混ぜ合わせた二人の唾液を、
クチュクチュいわせながら行ったり来たりさせる。
(あぁ、結菜とのキス、いい……。
すごく感じちゃう……。
結菜もバイト帰りで疲れてるはずなのに、
すごい積極的に舌を入れてくるし、
きっと私と同じ気持ちのはずだわ……)
抱き合って身体を密着させている分、
相手の悦びが直接胸に伝わってきていた。
お互いの気持ちが
どんどん高まっていっているのもわかる。
しかし、それゆえに、
双方が感じている物足りなさにも
自然と気付くこととなった。
交わされるキスが激しくなるにつれて、
二人の唾液の量が徐々に減ってきているのだ。
原因はおそらく、
急激な情欲の高まりからくる喉の渇きだろう。
(あんっ、唾が足りない……。このままじゃ、
せっかくのキスが続けられなくなっちゃう……)
その時、杏子の視線の端に、
テーブルに置いた水色のマグカップが映った。
あの中には、
飲みさしのお茶がかなり残っていたはずだ。
(そうだ! あれを口移しで飲めば、
キスを続けたままでいられる!)
とはいえ、
できる限りキスは中断させたくなかった。
そこで杏子は、
抱き合っての濃厚な口付けを続けながら、
少しずつ結菜の身体をテーブルの方へ
誘導していった。
「んっ、んんっ」
「んっ、んっ、んっ。んんっ」
お互いの口を激しく吸い合いながら、
テーブルの脇まで辿り着いた。
杏子は結菜の背中に回した腕に力を込めて、
彼女を座るよう促す。
「んはぁっ……! んじゅるっ!
んんっ、んんっ!」
「んふぅっ! じゅるるっ!
じゅるるっ、じゅるっ!」
カーペットの上に座り込んでからも、
二人の淫らなキスは、
息継ぎする時間すらもったいない、
といった調子で続いていた。
そうやって唇を重ね合わせたまま、
杏子はさりげなくテーブルのマグカップに
左手を伸ばしていった。
カップを倒さぬよう、
取っ手に慎重に指を通してから、
水平を保ちつつ顔の横まで持ってくる。
そしてカップの縁が頬に当ったことで、
ようやく結菜は杏子がやろうとしていることに
気付いたようだ。
「んふっ」
という吐息とともに、
結菜は何とも嬉しそうな笑みを浮かべて
口を離した。
すかさず杏子がカップの中のお茶を口に含む。
そして間髪入れず結菜に唇を重ね、
潤いをもたらす飲み物を相手の口へ注ぎ入れた。
「んんっ、ん……。んぐ、んぐ」
結菜がおいしそうに
そのお茶を飲み込んだのが分かる。
(ふふっ。やっぱりこの子、
私の唾だけじゃ足りないくらい喉渇いてたのね)
杏子もまた、口に残ったお茶を喉に流し込み、
気持ちの高揚からくる渇きを癒すのだった。
アンジェリークコラム